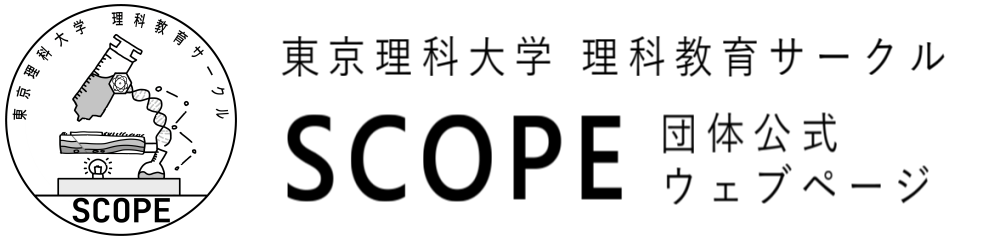初代代表挨拶
誰しも、科学に心を動かされた思い出があるのではないでしょうか。
私が幼少期を過ごした2000年代は、「第3次産業革命/デジタル革命」とも呼ばれるインターネットの本格的な普及やスマートフォンの興隆、ヒト全ゲノムの解明など、技術面でも価値観の面でも急激な変化が見られた時代の真っ只中でした。そんな「ワクワクできる」環境と当時の理科教育のおかげで、幼い私の中に科学への強い興味が育まれました。
ですが、高校生になる頃には法則の暗記や試験、課題に追われ、いつしか理科の面白さを忘れてしまっていました。しかしながら、当時私が苦手でありながら必死に覚えていた科学法則やその成り立ち、名称それこそが、理科を正確に捉え、正面から「ワクワクする」ために必要なものであることも確かでした。かつて抱いていた科学への興味との板挟みに苦しんだ経験こそが、大学入学後の私を理科教育へと駆り立てる大きなきっかけとなったのです。
「理科はもっと身近で、面白いものなのではないか」――これが私の理科教育への出発点となりました。
そんな中、私の興味を強く引いたのが、教職課程向け地学実験の講義を担当されていた関 陽児(せき ようじ)教授の実験でした。「何を見ても興味深い話が出てくる」と思えるほどの講義で、当時の私の心は大きく動かされました。しかし同時に、「こんなに面白い理科教育の講義があるのに、教職課程の受講者は年々減り続けている。しかも先生はあと数年で定年を迎えてしまう。この状況はあまりにももったいないのではないか」という思いが募り、教授に相談をしたことが「理科教育サークル SCOPE」設立の始まりでした。
こうした経緯から私たち SCOPE は、「理科の面白さをより多くの人と共有し、継続して楽しめるようにする」ことを目指し、
・実験・企画作成
・実験教室・出前授業
・教職課程互助
の3つを活動の柱に設定しました。
部員をはじめ、この団体に関わるすべての人が「理科がもっと好きになる」よう、リラックスして楽しめる場づくりを大切にしています。
ちなみに SCOPE という名前にはいろいろな意味が込められています。たとえば先頭の “SC” は “Science Communication” の略として知られ、科学技術の普及を通じてその面白さや課題を伝え、ともに知り、考えていくことを目指す活動「科学コミュニケーション」のことを示しています。また、SCOPE(スコープ)という単語には「日常に潜む理科の面白さを見つける、顕微鏡や望遠鏡のような、“視野”や“道具”としての役割を果たしたい」という願いも込めています。
また、実験教室やサイエンスショーというと、一見「子どもや一般の方々に科学実験を見せること」が目的だと思われがちです。しかしその本質は「コミュニケーション」にあります。飽くなき奥深いものです。単に実験を見せて「すごいね!」で終わるのではなく、「なぜそうなるんだろう?」という疑問や驚きを引き出し、それを理解へとつなげていくことが大切なのです。他の学生団体と異なり、東京物理学校からの伝統である、教職課程の学生が多く所属しているからこそ、こうした活動をより重視できる点も私たちの強みです。
加えて、私たちの大学には「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」という建学の精神が受け継がれており、SCOPE もその理念に通じる「理科の面白さを社会へ広げたい」という思いを大切に活動しています。
SCOPEはまだ誕生してから1年ほどですが、すでに多くの皆さまからご協力・ご応援をいただき、東京都や千葉県を中心に、各地の小中学校や科学館、公民館や児童館などでの理科実験イベント、大学のイベントなど、設立当時には想像もつかないほど幅広い場で活動を展開できるようになりました。
これからもメンバー一人ひとりが成長しつつ、社会や子どもたちに理科の楽しさを伝えられるサークルとして歩みつづけます。
最後になりましたが、活動を支えてくださる皆さま、そしてこれまでの活動に参加してくれているメンバーのみんなに、改めて心より感謝いたします。
私たちと一緒に「理科の面白さ」を社会へ広げていきませんか?
今後とも理科教育サークル SCOPEをよろしくお願いいたします。
2025年3月吉日
東京理科大学 理科教育サークル SCOPE 初代代表
創域理工学部生命生物科学科3年(当時)
中里 元
顧問挨拶
サークル代表がたいへん立派なご挨拶を申し上げておりますので、顧問からはごく簡単にお話を申し上げます。
(中里追記:そんな立派なこともないですけれどもね、、、)
ご縁あってこのサークルの顧問を引き受けましたが、おそらく数ある学生サークルの中でもかなり風変わりな部類になると思います。一言で言えば、理科実験を「楽しく」「分かりやすく」「しっかりと」やるサークル。また同時に、理科実験を「自分で楽しみ」「生徒さん・お客さんにも楽しんでもらい」「依頼者さんから頼もしいと思ってもらえる」サークルです。「理科実験」を軸に、授業実践力、教材開発力、コミュニケーション力、企画立案力、プロジェクト遂行力などなどを高めることが期待できます。何回やっても楽しい鉄板ネタ、苦労してやっとお披露目できるようになった自慢のネタ、お客さんから思ってもみなかった反応が…さあどーする? 自分で手を動かしてみて初めて分かる教具開発の難しさ・面白さなどなど。理科実験が好きなヒト、好きなような気がするヒト、生徒やお客さんと一緒に楽しく実験してみたいヒトは、是非、この風変わりなサークルをのぞいてみて下さい~
最後ではありますが、日頃よりご理解ご協力頂いておりますご関係の皆様には、心より感謝を申し上げます。月並みではありますが、これからも叱咤激励のほどよろしくお願い申し上げます。
2025年4月吉日
SCOPE顧問 教養教育研究院/理学研究科科学教育専攻 教授 関 陽児